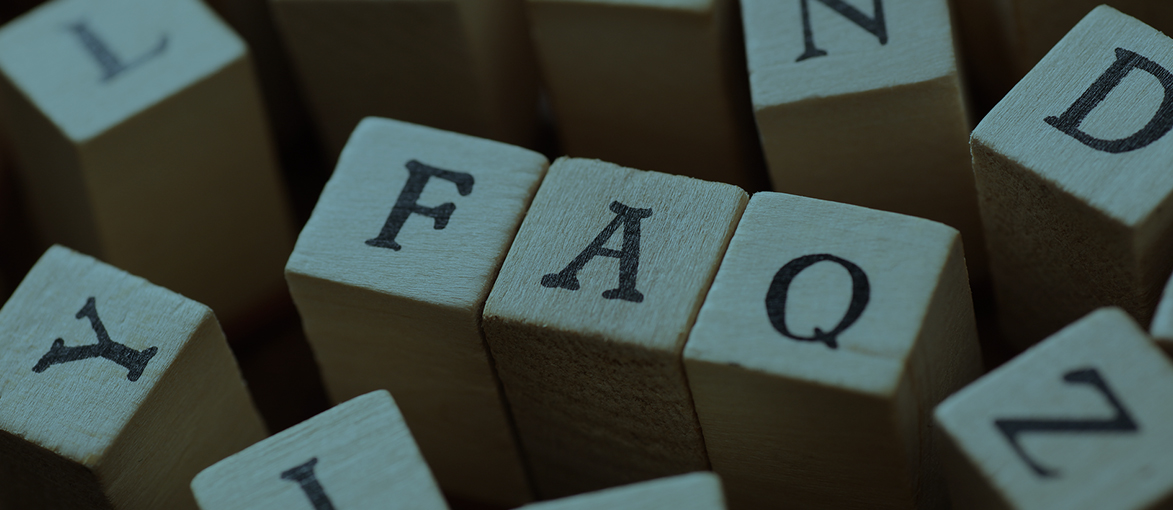
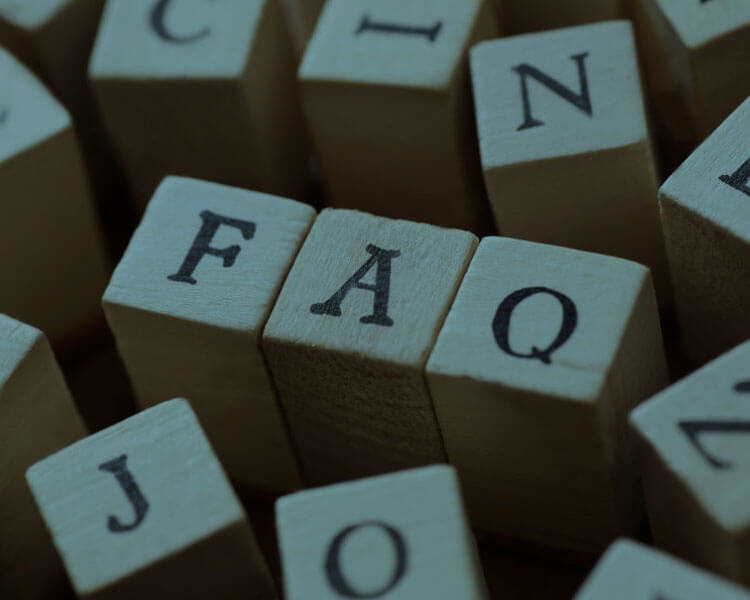

Q&A
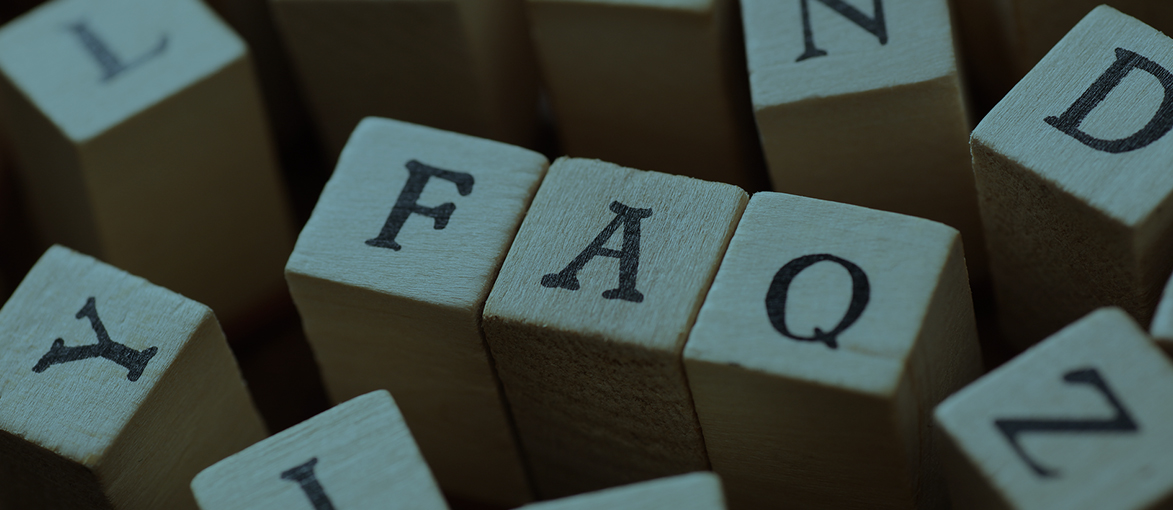
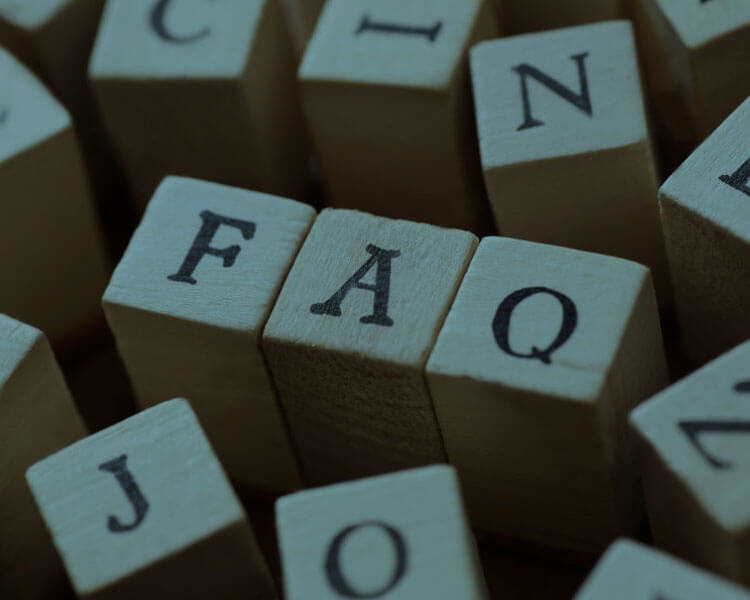

Q&A
印刷費の積算で、材料として用紙は別途算出しますが、
刷版材や印刷インキ等の材料費は、積算上、どうなっているのでしょうか?
印刷費の積算は、基本的に印刷物製作工程別に「数量×単価」を積み上げていきますが、一般的に、製版フィルム、刷版、印刷インキ、製本の糊等の材料費は、それぞれの工程別料金に含まれています。
用紙については、製作する印刷物ごとに指定された種類の用紙を調達する、印刷物製作費に占める用紙代の割合が比較的高い、等の理由から、材料代として積算項目になっていると考えられます。
校正作業で「責了(せきりょう)」とはどんなことですか?
校正作業は、ページや版のレイアウトが指示通りになっているか、誤字や脱字がないか等を確認する作業ですが、全ての校正作業を終え印刷できる状態になった時を「校了(こうりょう)」と言います。
通常、校正作業は印刷物発注側が確認を行いますが、校正作業を重ねて直し箇所が少ない段階でスケジュールの都合等を考慮して、最終的に印刷会社が責任をもって訂正・確認し校了とすることを「責任校了(責了)」と言います。
印刷の発注に当たり、複数の会社から見積もりをとったら、大きな差がありました。
安ければいいと思ったのですが、不安です。
原因は、①詳細な仕様を示していないため、受注側の解釈に大きな相違があった ②「受注実績を作りたい」等の営業戦略による見積り(一般的な水準とは異なる特値対応等)が考えられます。
①については、印刷の発注に、詳細な仕様を示すことが原則ですが、発注側が詳細な仕様書を作るためには、ある程度の専門知識が必要になります。そのため、事前に複数の専門家(印刷会社)に相談することが得策と思います。②については、印刷会社の考えから生じるものですが、当会発行の「印刷料金」を参考に水準をチェックし、乖離の大きい単価は確認しておく必要があります。
印刷物を発注したいのですが、どこに発注したらよいかわかりません。
どのようにしたらよいでしょうか?
印刷関連会社は、国内で約4万件弱あります。大手印刷会社は種類を問わず大量の印刷物に対応できますが、中小や零細印刷会社は各々が得意、不得意がありますので、適当に頼むわけにはいきません。
したがって、発注したい印刷物の種類と数量によって、大方の発注すべき印刷会社は絞られます。当財団では個別の企業の紹介はできませんが、当プラザ内でリンクしている印刷関連団体のWebサイトで組合員企業を検索する等の方法があります。
印刷物を発注し、校正段階で文字の差し替えや写真の変更を指示し、無事印刷物が出来上がりました。
請求書をチェックしたところ、当初の見積もりに修正代が加算されていました。
修正代はどのような時に発生するのでしょうか?
修正代は、発注者の指示により仕様変更(原稿の差し替え等)が行われた場合に発生します。例えば、発注者の指示により校正段階で写真の追加が発生した場合、当初の仕様に対し原稿内訳が変更となり修正作業が発生したことになりますので、修正代の対象となります。
印刷取引に当たり、最初にすべきことは仕様書を作成し、これを受発注双方で確認することが大切です。この仕様書に基づき、見積もりが作成され製作作業に入りますので、
仕様が明確であれば、作業がスムーズに進行するだけでなく、修正作業が発生した場合、どちらの責任から生じたものかを確認することも出来ます。
(積算資料印刷料金2025年版 一般印刷 op1 DTP修正 P.133)
印刷会社に文字原稿をデータで渡したら「レイアウト」をすると言われました。レイアウトとはなんでしょうか?
印刷会社は文字原稿を受け取ると、印刷の最初の作業としてレイアウトをします。レイアウトは割付とも言い、デザイン業務の一部として重要な作業になります。
レイアウトは、①見出し文字や主体となる文字の大きさ(ポイント、級数)・種類(書体)、②各ページへの原稿の割り振り、③罫票、写真、図版の大きさと位置、等をページ単位で決めていく作業で、作業は編集の専門家が行います。
アナログ原稿では「レイアウト用紙」によって指示しますが、DTP化してからはレイアウト用紙を使用せず、諸データ(文字や写真)をメイクアップする際に頭の中で考えながら同時進行する方法が増えています。レイアウト用紙を使用する場合は成果がみえますが、同時進行の場合は作業の成果がみえないので、デザイン業務としての料金の考え方は多様になっています。
Microsoft WordやExcelで文字や写真を配置したレイアウト済みのデータを作成し原稿として渡しましたが、何故そのまま印刷用データとして使ってもらえないのでしょうか?
現在、印刷用データの製作は主としてDTPソフトで行われています。DTPソフトは、イラストを作成するドロー・グラフィックソフト、写真を加工するフォトレタッチソフト、誌面構成を受け持つレイアウトソフトに大別され、それぞれに専用のソフトが用意されています。
ビジネスアプリケーションソフトであるMicrosoft WordやExcel等で作成したデータとDTPソフトではファイル形式、フォント種類等、様々な要素で違いがあり、そのまま印刷用データ(完全原稿)として製版・刷版工程で使用することは出来ないため、データ変換や修正、場合によってはDTPソフトで作り直しすることもあります。
なお、DTPソフトで作成したデータでも、ソフトやバージョン、OS等の製作環境の違いにより、データに不具合が生じる場合があるので注意が必要です。
文字入力の文字数は概算で算出してよいでしょうか?
文字数は、「1行あたりの文字数×行数×ページ数×段組数」で概算するのが一般的です。罫表や写真の挿入が予定されている場合は、その大きさから、該当する文字数(行数)を引いて計算することもあります。
各ページの正確な文字数は、改行の関係で異なりますが、上記の算出で割り切って考えます。
(積算資料印刷料金2025年版 一般印刷 B DTPパーツ作成 1.文字データ作成 P.106)
DTPの工程では色分解の掲載がありませんが、積算項目として必要ないのでしょうか?
色分解は、アナログ工程において、カラー原稿からCMYKの4色フィルムを製版する工程で発生する作業でした。現在のDTP工程では、システム上でCMYKへの変換が行われていますので、色分解という作業は発生しません。
文字デザイン校正紙の料金に、紙代は含まれていますか?
掲載の文字デザイン校正紙の料金には、用紙、トナー、インク等の材料費も含まれています。
(積算資料印刷料金2025年版 一般印刷 D 文字デザイン校正紙 P.137)
印刷物の発注にあたり、デザイナーに作ってもらったDTPデータを印刷会社に渡したら、
"データ受渡し書"の添付を依頼され、"プリフライトチェック"が必要と言われました。
"データ受渡書""プリフライトチェック"とはどのようなものですか?
DTPデータは、製作側と後工程側の製作環境(ハード、ソフト面)の違いにより、不具合が生じるケースがあります。データ受渡し書(「書式集 デジタル入稿仕様書」参照)は、DTPデータの製作環境や使用フォント等を記述するもので、これを添付することにより、データ受渡しのトラブルを防止し、後工程の作業がスムーズに進行します。
プリフライトチェックは、提供されたDTPデータが、印刷ルールに則った状態になっているか?このまま印刷物の製作を進めて良いか?をチェックする作業です。ちなみに、発注者から提供されるDTPデータは、基本的に何らかの修正作業が発生すると言われています。
(積算資料印刷料金2025年版 一般印刷 B DTPメイクアップ P.116)
印刷物の発注にあたり、デジタルカメラで撮った写真をデータ原稿として渡しました。
DTP製作において、デジタル原稿はデータ処理が必要と言われました。
データ処理とはどんなことをするのですか?
カメラのデジタル化が進んだ現在、写真原稿についてはデジタルカメラで撮影したデータを使用することが一般的です。写真データを印刷物の原稿とする場合、DTPソフトによる色のCMYK設定、サイズと解像度の調整、明るさ等の補正作業が行われます。これらの作業が“写真データ処理”に該当します。
(積算資料印刷料金2025年版 一般印刷 B DTPパーツ作成 4.写真データ作成 P.109)
色校正の説明で“DDCP”という用語を聞きましたが、どのようなものですか?
DDCPは“Direct Digital Color
Proofing”の略で、コンピュータのデータから直接色校正紙を出力することを指します。この意味では、インクジェットやトナー等の種類を問わず、色校正用としてのカラー出力の総称とも言えますが、印刷物製作においては、印刷の色を確認するため網点再現が可能な機種を指すことが一般的です。
DDCPは、網点の再現性、本紙(実際に印刷する紙)の使用、特色対応等の条件により、ハイエンドからローエンドまで様々な機種がありますが、その品質や料金は条件により異なりますので、色校正を行う場合は印刷会社に確認することが必要と思われます。
(積算資料印刷料金2025年版 一般印刷 op2 色校正 1.DDCP P.138)
カラー印刷物の色校正について、いろいろな方法があるようですが、どの方法が良いのでしょうか?
カラー印刷物の製作工程で行われている色校正の主な種類は以下のとおりです。
DDCP:色校正用の出力機から色校正紙を出力する手法
カラープリンタ色校正:一般的なカラープリンタで簡易的な色校正紙を出力する手法
平台色校正:色校正用のオフセット印刷機(平台色校正機)で色校正紙を印刷する手法
本機校正:実際のオフセット印刷機で色校正紙を印刷する手法
一般的には、印刷物製作工程のデジタル化とともにDDCPやカラープリンタの利用率が高まり、一方で、平台色校正は設備を保有する企業の減少により利用率は低くなっています。本機校正は、最も品質が高いものの、基本的には実際の印刷を行うのと同じであるため、コストが高くなります。
色校正に求める品質とコストにより選択する種類は変わってきますので、印刷会社の提案を受けながら、色校正の種類を決定することが必要になります。
(積算資料印刷料金2025年版 一般印刷 op2 色校正 P.138)
刷版には耐刷限度があると聞きましたが、この限度を超えて印刷するとどうなりますか?
またその限度を超える印刷を必要とする場合、どうするのでしょうか?
耐刷限度は、版材によって異なりますが、その印刷枚数は、「印刷料金」に掲載してあります。
刷版の選択は、印刷枚数によりますが、一般によく使われる枚葉印刷用の刷版の耐刷限度は7万枚、最も耐刷限度の高い輪用印刷用の刷版は20万枚と言われます。しかし、印刷版の内容やインキの使い方によっては、これを下回ることも上回ることもあり、一概には言えません。
耐刷を超えて印刷を続けると印刷がかすれてしまいます。限度を超えないところで同一版を用意しておいてそれに取り替える必要があります。これを版換えと言います。
(積算資料印刷料金2025年版 一般印刷 E 刷版 P.149)
伝票の印刷で印刷色に「赤」を指定したところ、特色扱いとなりました。何故でしょうか?
印刷は、C(シアン:藍)、M(マゼンタ:紅)、Y(イエロー:黄)、K(ブラック:墨)の4色(これをプロセスカラーと言います)をセットとして、これらを重ね合わせて様々なカラー印刷を行います。これらのプロセスカラーで再現が難しい色については、インキメーカーでラインアップされている特色を使用します。
「赤」はプロセスカラーのMと実際には違う色になりますので、特色扱いとなります。
なお、プロセスカラーを重ね合わせて希望する「赤」を再現することが可能な場合もありますが、その場合は印刷版として、重ね合わせるCMYKの色数分だけ刷版が必要になってしまいますので、1色や2色印刷でプロセスカラー以外を指定する場合は、一般的に特色を使用して印刷を行います。
(積算資料印刷料金2025年版 一般印刷 基礎知識 P.51)
A4判単色32ページの小冊子を1,000部発注したのですが、印刷会社より「部数が少ないので、
印刷料金は台数計算になります」と言われました。台数計算とはどういう意味ですか?
"台"は、ページ物印刷における、①印刷機に取り付ける刷版の数、または、②印刷機から刷り出される用紙(刷り本と言う)の数、の単位を言います。②の場合は製本工程における台数にも準じます。かつての活版印刷の時代、活字組版を木枠の台に載せて、印刷機に取り付けていた名残でそう呼ばれています。現在の刷版はアルミ版であるため、刷版の数の単位は“版”と言います。
印刷工程の作業手順は、1)印刷機に刷版と用紙をセット(取り付け)し、2)印刷機を回転して印刷しますが、印刷の単価は、1)2)を統合して、セット料込みの通し単価となっています。したがって、通し単価は、通し数が少なければ割高になり、多ければ割安になります。
印刷機械は、大量処理を前提としますので、一定の通し数に達しない場合は、通し単価を適用せず、取り付けた刷版1台(版)につき設定される最低基準料金を適用して算出します。これを“台数計算”と言います。
今回のケースでは、通常、仕上がり規格A4判を8ページ面付して、A1判の刷版を4版作成します。台数は、①刷版の数に準じて4台(版)、または②刷本の数に準じて2台(1色/1色:表1色、裏1色の意味)と言います。
最低基準料金(台数計算)となる通し数は、印刷方式、印刷機械のサイズにより異なりますので、本誌を参照ください。
(積算資料印刷料金2025年版 一般印刷 F 印刷 P.163)
オンデマンド印刷とは、どのような印刷のことを言うのですか?
オンデマンド印刷(Print on
demand)は、「必要な時に、必要なだけ、必要なところで出力」できるという考え方のもと、平版、活版といった印刷機を使わず、データから直接出力するデジタル印刷方式での印刷サービスを指して呼ぶケースが多いようです。
原稿データが完成すれば直接出力となりますので、短納期で印刷物を製作することができ、小部数にも適しています。このため、内容の変更が比較的多く、あまり在庫を持ちたくない印刷物では、古い在庫の処分といったリスクを回避することができ、在庫の縮小にも大きな効果が期待できます。また、刷版が不要のため、1枚ごとに異なるページデータを出力する可変データ印刷も可能です。
最近、印刷物の小ロット化や至急の発注が増大している市場環境で、急速に浸透しているところです。
(積算資料印刷料金2025年版 デジタル印刷 P.207)
ページ物印刷物の製本では「折り→丁合い→表紙→三方断裁」が
一連の流れとの説明を受けますが、それぞれの料金はどの項目に含まれるのでしょうか?
ページ物印刷物の料金項目は主に「本文加工料」と「表紙加工料」に分かれます。
一般的には、本文加工料には「折り→丁合い、三方断裁」の料金が、
表紙加工料には「表紙加工(くるむ、綴じるetc)」が含まれています。
(積算資料印刷料金2025年版 一般印刷 G 製本加工 P.172・P.176-177・P180-181)
輪転印刷したものを製本する場合、折る料金はどうなっているのでしょうか?
印刷機から出てくる印刷された用紙を「刷り本」といいます。輪転印刷機の刷り本は、すでに折ってある状態で出てくるため「折出し」といいます。刷り本が「折出し」のため、輪転印刷の通し単価には折り加工の料金も含まれています。一方で、本誌に掲載の製本料金の本文基本料・本文加工料は「刷り出し」を基本としていますので、「折出し」の場合は、折り加工の料金が重複してしまいます。このため、割増(引)事項に「折出し」の場合の割引率が記載されていますので、積算の際にはこの割引率を適用して下さい。
(積算資料印刷料金2025年版 一般印刷 G 製本加工 3.ページ物製本・並製本 P.176-177)
帳票を作成しますが、綴じたり糊付けしたりせず1枚ものとして仕上げる場合、
どの加工方法を適用すればいいでしょうか?
本誌では、帳票は「5.伝票製本」に区分されますが、このケースでは最終的に1枚もの(ペラ物)になりますので、「1.ペラ物加工 化粧裁ち」を適用して下さい。
(積算資料印刷料金2025年版 一般印刷 G 製本加工 1.ペラ物加工 P.169)
製本の「折り加工」に、断裁料金は含まれていますか?
含まれています。「折り加工」は、断裁後に、指定された折加工を施して完成します。本誌では、以前より「折り加工」の料金は「断裁+折加工」となっています。
(積算資料印刷料金2025年版 一般印刷 G 製本加工 1.ペラ物加工 P.170)
上質紙の用紙価格表では、判型が“四六判”と表記されていますが、
別の判型の用紙を使う場合はどうすればいいのでしょうか?
紙の原紙寸法は、主として“四六判”“菊判”“B(全)判”“A(全)判”の種類がありますが、掲載の判型は各品種における標準の判型・連量を表記しています。表記以外の判型で積算を行う場合は、洋紙連量表を参照してください。
なお、上質紙の掲載価格は“kg単価”ですが、判型によるkg単価の違いはありません(小口割増・規格外連量加算は別途)。
※連量について
連量換算表を見る(行単位で見る)と、例えば、四六判90kgの上質紙は菊判では62.5kgになります。
この○○kgという重量を“連量”といい、全判1,000枚(=1連)の重さを表しています。同じ厚みの紙でも判型(面積)の違いにより連量が異なるため、連量換算表で比較します。
(積算資料印刷料金2025年版 一般印刷 H 用紙価格 P.192)
予備紙の算出のための予備紙率が掲載されていますが、
製本予備紙の項目にある「付加加工」にはどのような加工がありますか?
用紙の数量を算出する過程で、通常、不可抗力として認められる範囲の数量を予備紙として加算しますが、製本予備紙の算出は、製本加工種類別に予備紙率が設定されています。
付加加工の種類は、「穴あけ」「切取りミシン」「光沢加工」等が挙げられます。それぞれの加工については、本誌 G 製本加工 6.付加加工(P.183~)を参照ください。
(積算資料印刷料金2025年版 一般印刷 H 用紙価格 製本予備紙率 P.197)
上質コート紙(A2)や軽量コート紙(A3)のA2、A3とは、どのような意味ですか?
A0、A1、A2、A3、B2、B3がありますが、塗工紙の略号として使われています。塗工紙は、上質紙や中質紙に白色顔料を塗工した用紙ですが、原紙が上質系のものはA、中質系のものはBの略号が付きます。数字は塗料の量を示し、数字が大きいほど塗工量が少なくなります。印刷物や紙の大きさを表す判型ではありません。
コート紙のマット調とはどのような紙ですか?
塗工紙(アート紙・コート紙)の表面の仕上りによる区分です。表面の光沢を抑えた低光沢・つや消しの仕上りを「マット調」、表面の光沢を高めた強光沢の仕上りを「グロス調」、両者の中間で、白紙部分はつや消し、カラー印刷部分が光沢となる仕上りを「ダル調」といいます。一般的に「マット調」は文字とカラー写真等が同一頁に並ぶ書籍等の印刷物に、「グロス調」は高級感を出したいカラーの印刷物に使用されています。
A4判の雑誌の積算について、表紙の表2・表3を印刷しない場合、用紙の正味数量の計算では
片面印刷として計算すればいいのですか?
ページ物の正味数量の算出は、「ページ数×製作部数÷全判から取れるページ数」で計算します。
質問のケースでは、たとえ表2・表3は白紙の状態でも、表紙は4ページになりますので、「4ページ×製作部数÷16ページ(全判から取れる両面分)」となります。
ちなみに、片面印刷と考えた場合でも、「1枚×製作部数÷4枚(全判から取れる見開きA3の枚数)」となり結果は同じになります。
両面印刷か片面印刷かは、印刷予備紙を計算する際に重要になります。
(積算資料印刷料金2025年版 一般印刷 H 用紙価格 印刷物製作にかかわる用紙費用の算出方法 P.194)
製本の予備紙で、複数の加工をする場合、予備紙率はどうなるのでしょうか?
予備紙率は、それぞれの加工における製作部数に対する予備紙の発生率となっていますので、それぞれの加工における予備紙率を合計して計算してください。
例えば、複写帳票に切取りミシン、穴あけ加工が加わる場合、複写帳 1.2%+付加加工(切取りミシン)0.8%+付加加工(穴あけ)0.8%=2.8%となります。
(積算資料印刷料金2025年版 一般印刷 H 用紙価格 製本予備紙率 P.197)
ナンバリング、穴あけ等を伴う大量の伝票の印刷を頼んだら一般の印刷機ではなく、
フォーム印刷機を使う」と言われました。
フォーム印刷は連続伝票の印刷と聞いていますが、一般の伝票も印刷するのですか?
フォーム印刷機は連続伝票用の印刷機械で、輪転印刷機のため大量印刷に向いています。また、穴あけ、ナンバリング等の付加加工が印刷と同時に行うことができるため、大量で付加加工作業のある伝票の印刷に応用される場合があります。最後の仕上げ加工において、連続伝票は連続して折り出されますが、一般伝票はシートカットされ、事務用印刷物の伝票として作成されます。フォーム印刷機械を設置している企業では、しばしばこのような対応をして合理化を図る場合があります。
穴あけ、ナンバリング等は、一般印刷機の場合、印刷機から排出された刷り本を製本・加工に入る前に加工するのが一般的です。
なお、フォーム印刷は、一般には業種別分類上、一般印刷とは区分されますが、伝票を作成するという用途別分類上、事務用印刷の範疇にあるとの見方もあります。
フォーム印刷で、面付けをした場合、
印刷通し数は、一般印刷のように、面付けの数で割っていいのでしょうか?
フォーム印刷の印刷工程での単位は、印刷機を"通す"数ではなく、印刷機から"折"出される数です。
横の面付けにおいては、印刷機械より一度に面付け数分だけ折出されますので、折数は"製作枚数÷面付け数"となりますが、縦の面付けにおいては、印刷通し数ではなく
折出し数をカウントしますので、面付け数に関係なく、折数は製作枚数に準じます。
製作枚数1万枚の場合、縦2面付けは製作枚数に準じ"1万折"ですが、横2面付は製作枚数を÷2面付け=5,000折となります。ただし、フォーム印刷機は印刷幅の制限やマージナルパンチ(送り孔)の加工により、横の面付が不可能なこともあるため注意が必要です。
(積算資料印刷料金2025年版 フォーム印刷 D 印刷(折) P.305)
クリエイティブワークとは
クリエイティブワークとは、広報活動などの「課題解決のためのコミュニケーション戦略活動」をさします。
単純なデザイン、DTP制作とは異なり、ターゲットに対し製品やサービス、事業概要などの情報を効果的に伝えるために、メディアセレクトを含めた戦略活動全般で行います。
クリエイティブワークはどこに(誰に)依頼すればよいでしょうか
クリエイティブワークは、メディアセレクト(バイイング)を行う「プロデューサー」、クリエイティブ全般の責任、指揮をとる「クリエイティブディレクター」、「アートディレクター」、マーケットの分析等を行う「マーケッター」、プランニングを元にデザインを起こす「デザイナー」、「コピーライター」などのさまざまな専門領域が重なり合って進行していきます。
これを全て一社で任せられるとすれば、総合広告代理店ということになります。
昨今では、メディアバイイングを除いた業務を担うクリエイティブブティック(クリエイティブエージェンシー)という形態も増えつつあります。
また、印刷会社やWeb制作会社がクリイエティブワークの業務を含めて、印刷物やWeb等のメディアを制作することもあります。